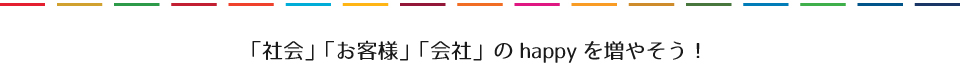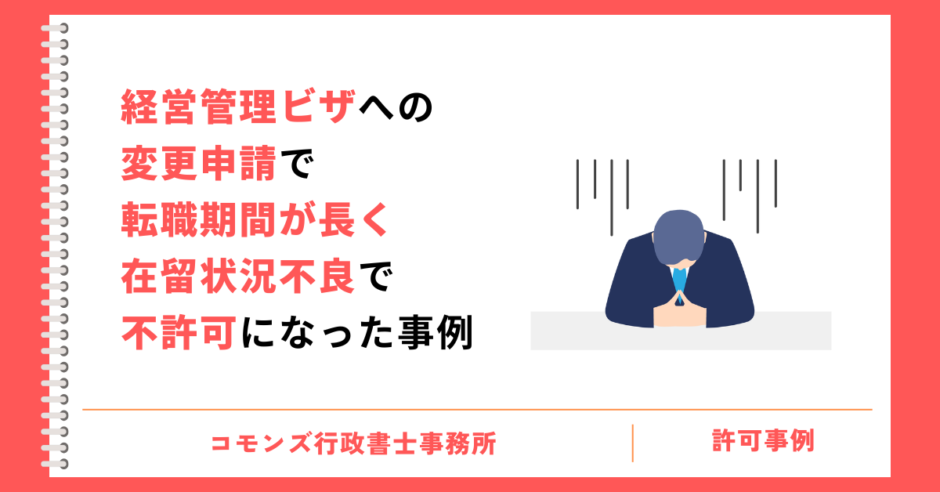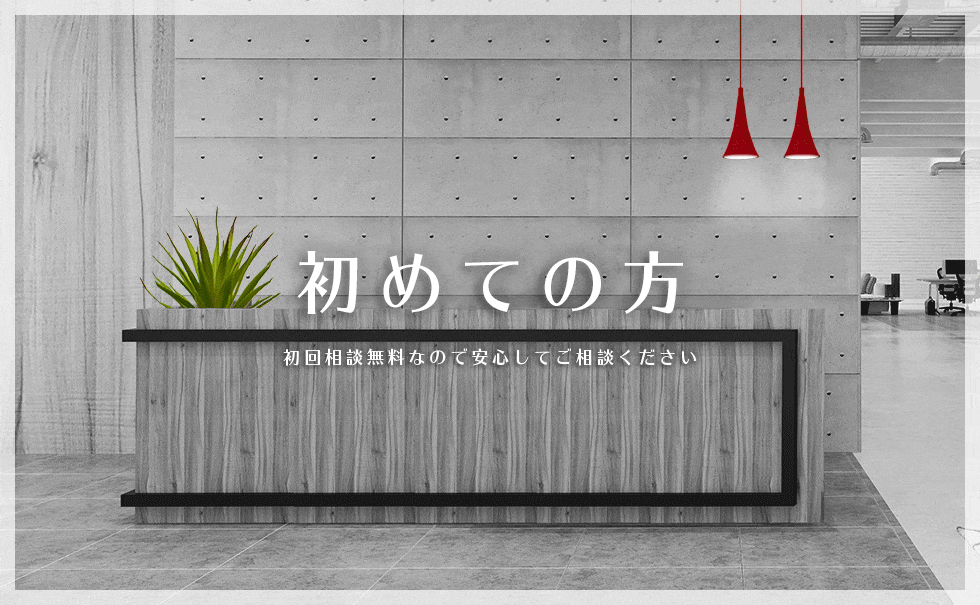経営管理ビザ申請の不許可理由と再申請の対策とは?
経営管理ビザが不許可になってしまったら、第一にすることは不許可理由をしっかり把握することです。
経営管理ビザ申請は、ビザ申請する前に資本金を出資して会社設立を行い、事務所を借りて事業が開始できる準備を整える必要があります。そのため、リスクがとても高いビザ申請になり、そのリスクを承知でビザ申請に挑むことになります。
「不許可になる確率を下げ、許可になる確率を上げたいなら、コモンズへご相談ください!(初回相談無料)」
[ご案内]2025年10月16日より、経営・管理ビザの要件が大幅に改正され、3,000万円以上の資本金が必要、1人以上の常勤職員(日本人、永住者ビザ、配偶者ビザ、定住者ビザのみ)を雇用することが必要、申請者又は常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有することが必要などの変更が行われました。当事務所ホームページの該当ページは順次更新を行ってまいります。
経営管理ビザ申請の不許可理由の把握と再申請の対策まで全てサポート!

コモンズは、ご相談件数が年間3,000件越えという日本トップクラスです!
ご依頼ポイント
経管認定
初回相談無料
返金保証あり
追加料金なし
日本全国対応
許可率98%以上
コモンズは常にフルサポート
- 許可率・実績ともに日本トップクラス企業!
- 再申請で逆転許可を狙うならお任せください!
お問い合わせ(相談無料)
経営管理ビザ申請の不許可理由13項目
- 【事務所】日本国内に事業を営むための事務所がない(レンタルオフィスで区画が曖昧、オフィスの実体がない場合も含む)
- 【事務所】事務所の賃貸借名義人が申請する人の個人名になっており法人名に変更できない
- 【事務所】事務所・店舗の使用目的が事業用になっていない
- 【事務所】事務所と自宅兼用の場合は公共料金等の支払い及び出入りの動線に関する取り決めが明確でない
- 【要件】500万円以上の資本金または2名以上の常勤職員がいない
- 【要件】実際は経営・管理以外の業務をしている
- 【要件】複数人が経営管理ビザを取得する場合、その事業規模や必要性がない
- 【要件】出資金や経歴などを証明する書類を準備することができない
- 【要件】過去のビザ申請で提出している書類の内容との整合性がない
- 【事業計画書】事業計画書がしっかり作成できていない
- 【事業計画書】事業の継続性が見込めない内容である
- 【ビザ更新】経営状況が赤字や債務超過であり、事業の継続性が見込めない
- 【ビザ更新】最初にビザ申請した内容から変更箇所が生じている
不許可理由13項目を詳しく解説
- 【事務所】日本国内に事業を営むための事務所がない(レンタルオフィスで区画が曖昧、オフィスの実体がない場合も含む)
経営管理ビザで事務所の確保は皆さん困られています。今はインターネットで事業をすることができるので事務所の家賃を安く抑えたいという考えから、レンタルオフィスやバーチャルオフィスを利用するケースが増えてきました。また、会社が設立していないからオフィスを貸してもらえないということもあります。どちらにしても、経営管理ビザを取得するためには事務所は必須条件になっています。レンタルオフィスで完全個室になっていない場合や仕事で使う機器を共有している場合は不許可になることがあります。バーチャルオフィスも同様で事務所として認められず不許可になることがあります。 - 【事務所】事務所の賃貸借名義人が申請する人の個人名になっており法人名に変更できない
経営管理ビザは、株式会社を立ち上げる前に事務所を借りる流れになります。ここで問題になるのが最初は個人名義で事務所を借り、株式会社が設立したら名義を個人名義から法人名義に切り替えなければなりません。そもそも個人で事務所を借りるハードルが高いという点や不動産屋に借りるときに名義変更の説明をしていなかったために名義変更できないという問題も発生します。 - 【事務所】事務所・店舗の使用目的が事業用になっていない
賃貸借契約書の使用目的が住居用になっているケースをたまに見かけます。仕事ができるスペースがあるので大丈夫と安直に考え、不動産屋から事業用に変更してもらえない場合は事務所として使えません。住居用はあくまでも住居なので、契約する前に事業用になっているか確認しなければなりません。 - 【事務所】事務所と自宅兼用の場合は公共料金等の支払い及び出入りの動線に関する取り決めが明確でない
自宅の一部を事務所として使いたい場合に起こる問題ですが、住居で使うスペースや動線が仕事で使うスペースや動線としっかり区分けできていなければなりません。住居スペースを通らないと仕事スペースに行けない場合はダメです。また、光熱費などの公共料金も仕事とプライベートの支払い割合を決めておかなければなりません。 - 【要件】500万円以上の資本金または2名以上の常勤職員がいない
ほとんどの方が500万円の資本金で経営管理ビザ申請を行っています。この500万円の原資の出所が不明な場合は不許可になることがあります。例えば、自分で100万円を貯めて残りの400万円を親から借りたと主張する場合、親が400万円を貯めることができた根拠が必要になります。友人から借りた場合は更に厳しく審査されます。また、資本金は500万円が最低限必要ですが、実際手持ち金は600万円ぐらいなんだかんだで必要になると思っている方がいいでしょう。 - 【要件】実際は経営・管理以外の業務をしている
経営管理ビザ以外の業務とは何かを知ることが大切です。料理店が分かりやすいですが、料理することは経営管理ビザに該当しません。料理は技能ビザに該当するので料理人を雇う必要があり、自分で出来るからといっても料理したらダメです。 - 【要件】複数人が経営管理ビザを取得する場合、その事業規模や必要性がない
これは実際のところ親や友人のビザのために検討している外国人が多いです。売上も年々増加して従業員も増え、拠点も増えているならもう一人経営管理ビザで人材が欲しいとなるのは分かります。しかし、無茶な理由をつけてもう一人経営管理ビザで人材が欲しいというのは無理があります。本当にもう一人経営管理ビザの人材が必要なら許可になりますが、経営管理ではなく一般的な従業員で十分できる仕事内容の場合は不許可になります。 - 【要件】出資金や経歴などを証明する書類を準備することができない
経営管理ビザは全て書類審査になるので、根拠となる資料が必要です。履歴書で書いている内容を証明する公的な書類や、取引が見込める会社との契約書など全て根拠となる公的な資料が必要になります。資料がなければ、ただ言っているだけとなって不許可になります。 - 【要件】過去のビザ申請で提出している書類の内容との整合性がない
過去に経営管理ビザでもそれ以外でもビザ申請したことがある外国人は、その書類に書いた内容との整合性も重要になります。過去に書いた内容と今回の経営管理ビザ申請の内容が異なると不許可になります。 - 【事業計画書】事業計画書がしっかり作成できていない
事業計画書に書いている内容が適当で、たらればになっているとダメです。また、数字も根拠がないと絵にかいた餅になり、信ぴょう性がありません。事業計画書は、これから事業を始める経営者の想いやアイデア、ビジネスモデルやビジネスプランがしっかり書いていて当然のものになるので、とりあえず日本で暮らすために経営管理ビザが欲しいという方は、この事業計画書で不許可になります。 - 【事業計画書】事業の継続性が見込めない内容である
事業計画書の内容によっては事業の継続性や安定性が見込めないケースがあります。もっと市場調査をしたり、売上予測を具体化させたり工夫する必要があります。更に、細かい数字や実現性にもこだわって同業他社の勉強ももっとする必要があります。 - 【ビザ更新】経営状況が赤字や債務超過であり、事業の継続性が見込めない
事業が軌道に乗っていればいいですが、赤字の場合は経営管理ビザの更新が厳しくなります。赤字でも回復が見込めるならその点をアピールして更新に挑みますが、債務超過になっている場合は更新ができないことも十分あり得ます。 - 【ビザ更新】最初にビザ申請した内容から変更箇所が生じている
事務所を移転した場合や、当初予定していた事業以外の事業をしている場合など、経営管理ビザの要件からはみ出ていることがあります。はみでており、修復できない場合は不許可になります。経営管理ビザは細かい条件をクリアして許可になっているので、少し変更点があっただけでも経営管理ビザから見ると大きな変更点になることもあるので注意が必要です。
出入国在留管理局が経営管理ビザの外国人経営者の在留資格基準の明確化について公表しているのでリンクを貼っておきます。
外国人経営者の在留資格基準の明確化について
出入国在留管理局が経営管理ビザの要件の解釈について公表しているのでリンクを貼っておきます。
在留資格「経営・管理」について
不許可になったらすぐにやるべき対策を教えます!
- 経営管理ビザが不許可になったら不許可通知書を確認して、連絡先の出入国在留管理局に電話で訪問日の予約をします。
- 予約日に出入国在留管理局へ行って担当官から不許可理由を確認します。しかし、担当官は不許可理由を親切に全て教えてくれません。なぜなら、不許可理由を全て教える義務が出入国在留管理局にないからです。そのため、担当官から不許可理由を聞きだす努力が必要になります。
- 再申請に向けて、何が解決したらいいか?いつごろ再申請したらいいか?も必ず確認しなければなりません。これも聞かなければ教えてくれません。
再申請の対策
- 再申請は、不許可になった原因を解消させてから行います。前回と同じような申請書を提出してもまた不許可になるので、詳しく説明が必要な箇所は補足説明書を別途作成したり事業計画書の見直しをします。
- 不許可になった理由の全てが分からない場合、弊所にある過去の膨大なデータと照らし合わせて改善点を探していきます。不許可後の再申請は時間と労力がいるのでお客様と一緒に許可を目指して走っていきます。
実際にあった経営管理ビザ申請が不許可になった事例をご紹介
日本でIT会社の起業をするために経営管理ビザ申請をして不許可になった事例です。
申請者は、日本で技術人文知識国際業務ビザを持って暮らしておりましたが、会社を辞めて転職活動をしていたがなかなか就職先が見つからず、最終的に自分で会社を経営することにしました。しかし、会社を辞めてから経営管理ビザ申請まで半年以上経過しており、在留状況に問題があるということに加え下記理由で不許可になりました。
①半年以上在留資格で認められた活動をしていない
②資本金の500万円の出どころが不透明
③前職の退職理由を嘘ついていた
まとめ
不許可になっても、再申請で許可になることはたくさんあります。不許可になる多くの場合が上記で解説した内容をクリアしていないことが原因です。弊所は経営管理ビザ申請の許可実績を多数持っており、お客様をフルサポートしておりますので不許可になる前にご相談いただければと思います。(初回相談無料です)
役立つ情報
【経営管理ビザ申請の情報】
| 経営管理ビザの人口 | 全体の9割がアジア人 |
|---|---|
| 在留期間 | 5年、3年、1年、6月、4月又は3月 |
【経営管理ビザの国籍別ランキング】
| 中国人 | 20,551人 |
|---|---|
| 韓国人 | 2,725人 |
| ネパール人 | 2,691人 |
先生の一言

代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka最初にお話ししましたが、経営管理ビザはリスクが高いビザ申請になります。
事務所を借りて、会社設立をして、備品を購入して、取引先を探して、ホームページも用意して、開業準備をたくさんした後でやっと経営管理ビザ申請ができます。これで不許可になると事業を開始できないのでたまったものではありません。
弊所は、ビザの専門家として経営管理ビザに関する豊富な実績と経験を持ち、お客様をしっかりとサポートできる体制を整えております。日本全国をサポートしておりますので、ぜひ弊所にお任せください!
こちらもおすすめ
国籍別にページをご用意しました
私たちコモンズのご案内